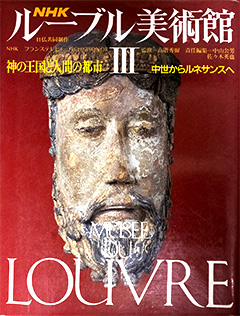カレーの市民 1884-88年 ブロンズ , オーギュスト・ロダン , 国立西洋美術館, 東京
The Burghers of Calais 1884-88 (model), 1953 (cast) (bronze) , Auguste Rodin , The National Museum of Western Art, Tokyo
(Nikon D7000 + Ai AF Nikkor 35mm f/2D)
「アート」
自らの身分を言い表すとき、俗に〇〇系男子や〇〇系女子などと言われている。最近であれば〇〇系ユーチューバーという言葉(もはや少々野暮ったいが)が使われている。こうした記号で、私自身を表そうとしたとき、「社畜系会社員」といういささか自嘲気味な言葉が頭に浮かんだが、今後景気が悪化し続ければ、社畜でさえも居られなくなり、畜舎から摘み出される可能性もある中、思えば1992年から「失われた何十年」とほぼ同じ期間を社会人として過ごし、随分と難儀な時に社会に出てしまったなと思うこともあるが、私よりも若い世代は就職氷河期などさらに厳しい期間を過ごしており、長く働くことができただけ感謝しないといけないと、実家への帰省をやめて、長くなったお盆休みの間、しみじみと考えていたわけである。
さて、話は変わるが、ここ最近の傾向として「アートはよくわからん。教えろ」と各方面から言われる事が多くなってきている。私自身、こう見えても美術系の大学を卒業しており、こうした問いには真摯に応えないといけないのではあるが、私は現在のところ画家でも芸術家でも写真家でも評論家でもないただの社畜系の身分なので、この問いに対しては、日本においてカタカナで「アート」と書かれている書籍なり雑誌なりイベントは怪しいものが多いから近付かないほうがいいですよ、と優しくアドバイスしてきたのだが、あまりいい加減なことばかり言っているとそろそろ怒られそうなので、私自身の経験を語りつつ、少し書き残しておく。
美術との出会い
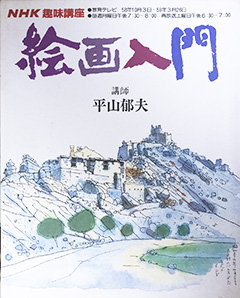
1983年10月から84年3月まで放送。先を尖らせた竹箸のようなペン先に墨をつけて、クキクキっと輪郭線をひき、水彩を滲ませながら描いていくのが印象的であった。
1985年から86年にかけて放送。イギリスやフランスの男女の名優が小粋な会話をしつつ作品を紹介していた。
私が美術教育を受けたのは1980年代前半から後半にかけてである。美術・芸術系に入り込むきっかけは、おそらく多くの人と同様に授業で描いた絵が美術の先生に褒められたことからだ。その授業はマグリットの絵をいくつか見せられたのち、同じように自分の頭の中に浮かんだ空想を実際の絵にしてみようという課題(今から思えば中学にしては難解な課題だった)。私はそのとき、巨大なスプーンを描き、その上に雨が降り注いで滝のようにスプーンから水が流れる場面を描いたのだ。担当の美術の先生がそれを見て、「雨は何本か斜めに線を引くといいぞ」と助言してくれた。当時なぜそんな風に描くのが良いのか不思議に思ったものだが、それは広重の雨の表現だと知ったのは随分後のことだ。そのまま、水彩や油絵にのめり込み、高校生になっても描き続け、美大専門の予備校に通い、関東の美術大学に行くことになるのだが、このような歩みは現在でも多くの画学生と同じであろう。当時テレビではNHKで平山郁夫画伯が「絵画入門」という趣味の講座の30分番組を行なっており、また、最近亡くなったエンニオ・モリコーネのテーマ曲が印象的なルーブル美術館というNHK特集などもあった。その頃発売されて間もない高価なビデオデッキを買ってもらって、現在から比較するといささか残念な画質ではあるがVHSテープに毎週かかさず録画していた。NHKの日曜美術館では高階秀爾氏や若桑みどり氏がミケランジェロ等ルネサンス芸術について熱く語り、また、システィーナ礼拝堂の修復のドキュメンタリーをワクワクしながら見ていたものだ。
バブル前夜であり、現在と比べても芸術・美術分野の各メディアでのコンテンツは豊かであったと思う。その後私は上京し関東の美術大学に通うことになるのだが、それら話は現代美術のことを書くときにしよう。1990年代以降、平山郁夫画伯も若桑みどり氏も、思想信条や自身の立場などにより業績とは別のところで批判され、悪評をたてられたことが記憶に残る。今風に表現すると炎上というのだろうか。私が若い頃必死になって見ていたメディアで活躍されていた先生達が、非難をされているのを見るのは悲しいものだ。
近代以前の美術・芸術を語ること
一般的に芸術・美術を論ずることは、その国の歴史・政治・宗教・思想・哲学を踏まえた上で当時の世相・風習などあらゆる方面から解釈しなければならず、知ったかぶりをしようものなら、あっという間に教養の浅さが露呈してしまう。NHKで放送されたルーブル美術館の録画テープを擦り切れるほど観た私も、現地で長期間研究された若桑みどり氏の前では、ただの無知の知ったかぶりに等しい。彼女の著書の中で引用される膨大な書籍の数々に圧倒されるが、「イメージを読むー美術史入門ー」のあとがきに、本格的に学ぶためには日本美術を学ぶ人でさえ外国語の習得が不可欠と語っている。さらに西洋美術史を深く研究するには、英、独、仏、伊語は最低限必要と。これは専門的に美術作品を論評する為に必要であろうと思われるかもしれないが、こうした美学・美術史学は長く続く学問の上に成り立っていると認識しておく必要がある。当時バブルで日本が豊かになったと思われていた時でさえ、国内において美術・芸術の学問はまだまだ底が浅い、貧弱なものであるということに、彼女の目には映ったのではないだろうか。
では知識がない者は美術の鑑賞したり語ったりしてはならないのか、と怒られそうだが、そうではない。もちろん予備知識があればより深く接することができるが、軽く見過ごしたものに深い意味が込められていることがあり、むしろほとんどわからないものだらけだと思っておいた方が良いかもしれない。その場合、これはと思った作品をできるだけ記憶しておく。できれば、どのように描かれて(作られて)いるか、どの時代のどのような人物が描いたかを、インクの出るペンではなく鉛筆で細かく書き留めておく。その日観てきたものを日記などに残しておくと良い。そして、後日、観てきたものについて調べる。映画や小説、舞台等で似たような場面や図像が出てきたとき、どんな文脈で使われたか、調べる。違う年代で、違う国で似たような図像が使われていたとき、さらに調べる。このようにして同時に歴史・政治・宗教・思想・哲学について知識を広げていけば良いだろう。
歴史を表したものや記録性の強いものはしっかりと下調べをして鑑賞した方がより理解が深まるのは当然であろう。しかし一方で、近代以前の日本で生み出された作品の中で、頭の中を無の状態で対峙した方が良い場合の作品もある。これはあくまで私個人の見方なのだが、例えば、国宝にもなっている大変有名な久隅守景の納涼図屏風がある。和歌から着想されたとか、作者の守景は狩野派を破門されたとか、そのようないくつかの情報を全て除き、己を無にして、ただただ対峙する。すると単なる素朴な家族が寛いでいる図が、この世の中になぜ人はいるのか、自然の中の人間の関わりなど、この世のありのままの姿が全て頭の中にストンと入ってしまうような、こうした見方をすることができる。日本人である我々はこちらの方が馴染み深いかもしれない。ただ、鑑賞する側はこれでよくても、目に見えないものを生み出す表現者になるには、結局自問自答を繰り返し達観するまで勉強しなければならないのは言うまでもない。
いずれにせよ、近代以前の芸術作品には、西洋と東洋(この区分けは多分に大雑把過ぎる区分だが)では底流には全く違うものが流れている。古代ギリシャ・ローマ、初期キリスト教、新プラトン主義などから流れてくる西洋思想と、古代インド・バラモン教、ウパニシャッド、そして仏教等からくる東洋思想。現代人は少々、思想や宗教を軽視する傾向があるが、まずこれらを押さえておかないと、不十分な理解のままになってしまうだろう。
如来坐像(片岩),クシャーン朝・2〜3世紀 パキスタン・ガンダーラ 東京国立博物館
Seated Buddha (Schist) , 2nd-3rd century Gandhara, Pakistan Kushan dynasty , Tokyo National Museum.
(Nikon Z 7 + NIKKOR Z 50mm f/1.8 S)
出典・参考文献