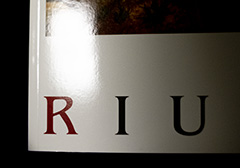Nikon Z 7 / NIKKOR-S.C 1:1.5 f=8.5cm
岸田劉生展
東京ステーションギャラリーで開催されている「没後90年記念 岸田劉生展」に行った。当展は劉生初期の作品から年代順に沿って展示されているのが特徴で、彼の作風の変遷がよくわかる非常に興味深い展覧会であった。
岸田劉生の初期の作品はポスト印象派(昔は後期印象派と習ったが今は違うのか)の影響が色濃く見える。筆のタッチは荒々しく、ゴッホに似た風の自画像はユーモラスにも見える。そして麗子が誕生する時期にかけてよりクラシックに感化された作風に変化していく。雑誌・白樺でマチスやセザンヌが紹介され、海外からの新しい芸術が日本にも席巻するなか、この近代的傾向から離れていき、さらに東洋芸術の卑近美に変わっていく過程に私は強く興味を惹かれる。劉生は自分が欲する表現に自ら従ったとされる。現在主流である手法から、いかに脱するか。写真を表現手段としている人にとっても大きなヒントを与えてくれる展覧会だろう。
図録の色味
私の仕事柄どうしても気になってしまうのが、図録に掲載されている作品と実際の作品の色味の違いだ。印刷のCMYKに変換する以上全く同じにすることは困難なので仕方がないのだが、それでも何点か実際の作品よりかけ離れたものがある。「林檎三個」は図録では少し明るく印刷されているが実際は暗く静かな雰囲気の絵だ。「麗子坐像」は図録では服の赤色が渋く沈んで見える。実際はもっと鮮やかな赤だ。以前セザンヌの「赤い肘掛椅子のセザンヌ夫人」を実際に観た時、それまで画集などで見ていたものとは全く違う、絶妙な色彩の配色に目から鱗が落ちた経験があるが、自分の目で鑑賞しないと実際に作品に触れたことにならないというのは、今回も強く思った次第である。
東京・丸の内の東京ステーションギャラリーで10月20日まで。
Nikon Z 7 / NIKKOR-S.C 1:1.5 f=8.5cm